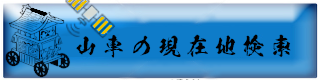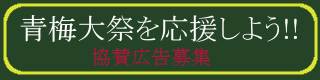|
| 1369年(応安2年) |
| 1513年(永正10年) |
|
祭礼が行われています。 |
| 1872年(明治5年) |

|
| 1873年(明治6年) |
| 1878年(明治11年) |
| 1899年(明治32年) |
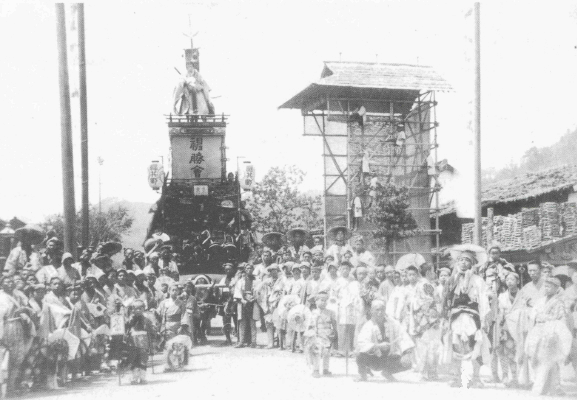
|
います。 |

|
| 1910年(明治43年) |

|
| 1911年(明治44年) |
| 1912年(明治45年) |
| 1915年(大正4年) |

|
| 1946年(昭和21年) |
| 2011年(平成23年) |
| 2019年(令和元年) |
 |
| 2020年から2022年(令和2年から令和4年) |
その後現在まで、500年の歴史を誇る伝統と文化は受け継がれ、これから先の世代へと引き継がれて行くのであります。 |
|
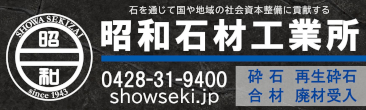  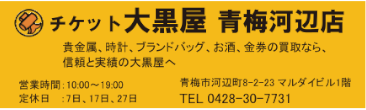   |
|
| 青梅宿『青梅村』に位置する住吉神社は住吉山延命時の鎮守として応安2年6月に創建され、その後永正10年3月28日(1513年室町時代)青梅村鎮守の神様となりました。村民が拝殿等の改修工事を施工し、その完成を祝い5町の氏子村民多数が祭り事を計画し実行しました。これが春季例大祭の始まりと言われ、現在の山車巡行祭礼となりました。 |
| 住吉神社の氏子である5町(現在山車人形を所有する住江町、本町、仲町、上町、森下町)で山車を曳いたのが青梅大祭の始まりです。 |
| 山車人形は江戸末期に青梅の産業であった青梅縞などで活況を呈していた商人たちが買い求めたと言われています。山車人形は江戸の人形師たちが腕を振るった傑作揃いで、明治の終わりまでは山車の上に高く飾られて巡行し、豪華絢爛を謳われたものです。その後、電線が張られるようになると山車は現在の屋台の形での巡行になり、人形は町内に飾られるようになりました。戦後になり、滝ノ上町、大柳町、天ケ瀬町、裏宿町そして西分町、勝沼町、日向和田も加わり、現在の12台の巡行となっています。 |
| 青梅大祭の見所は、華やかな衣装で山車を先導する拍子木と手古舞、粋ないでたちで唱ずる町内衆の木遣り、山車が行き交うときの競り合い(ひっかわせとも言う)は祭りのもうひとつの見所、それは青梅ならではのケンカ囃子と呼ばれている威勢のいい囃子、また街道を埋め尽くす露店(露天)の数々(300超出店)。 |
| 古式床しき伝統行事を守りつつ青梅大祭は今後も挙行されてまいります。 |
| なお、5町の人形とその衣装等は【青梅市指定有形民俗文化財】に指定されております。 |
|
| 青い森の恵み |
|
Copyright @ 2025 青梅大祭実行委員会. All rights reserved |